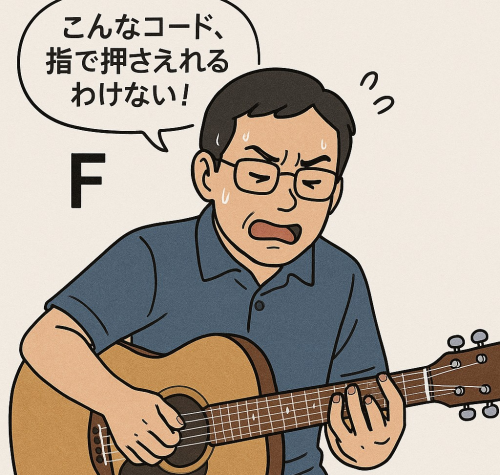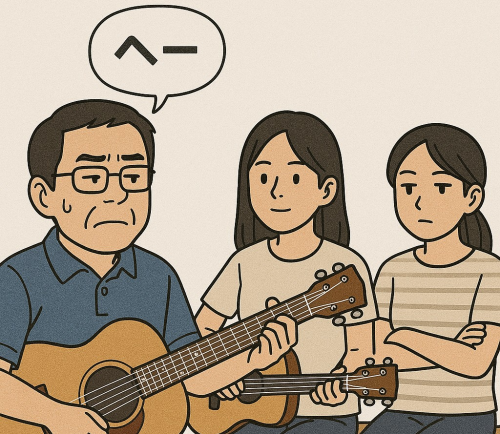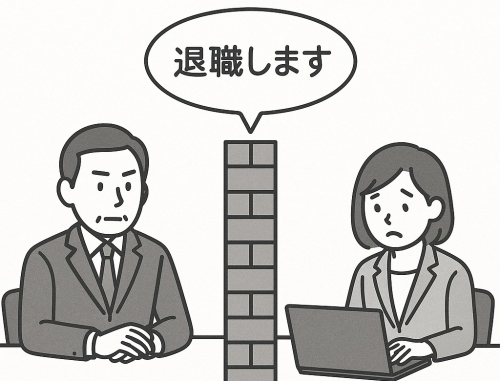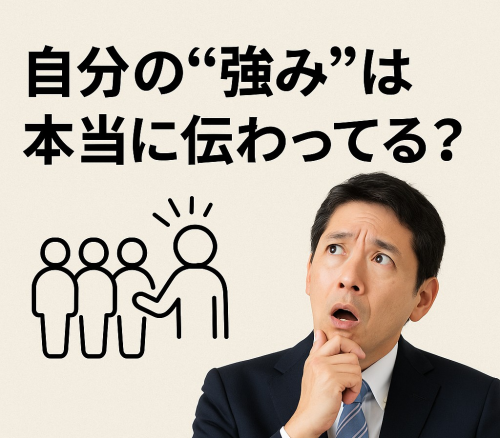ブログ
雑談と報連相だけでは組織は強くならない
最近、職場での「コミュニケーション」について
考える機会がありました。
「昨日のあのニュース知ってる?」
「うちの娘がさ~」
こうした雑談は相手を知るきっかけになりますし、
関係性づくりには欠かせません。
一方で、
「このクライアントから相談を受けたんだけど、どう対応すればいいだろう?」
「あの案件、進捗状況はどんな感じ?」
といった業務上の会話も、仕事を円滑に進めるためには大切です。
ただ、これらの会話は多くの職場で自然と発生します。
では、それだけで本当に十分なのでしょうか?
結論から言うと――十分ではありません。
例えば、こんなシーンを見たことはないでしょうか。
社長:「今期から○○という取り組みをしよう!」
社員:「……」(内心:めんどい、やだな…)
あるいは、
上司:「君にこの仕事を任せたい」
部下:「え?私がですか?」(なんで私なのよ!)
いざという時に一体感や向上心が欠けている…。
社長や上司からすれば「裏切られた」ような気持ちになる。
実際、こうした場面は少なくありません。
これは、表面的なコミュニケーションをどれだけ積み重ねても、
肝心なときには役に立たない、ということを示しています。
ここでヒントになるのが、
チェスターバーナードが提唱した「組織成立の3要素」です。
①共通の目的(ビジョン、計画)
②協働意思(貢献意欲)
③コミュニケーション
私自身、ある組織で働いていた時のことを思い出します。
与えられた仕事はきちんとこなしていましたが、
周りのスタッフがどれだけ熱量を持って取り組んでいるのか、
まったくわかりませんでした。
周囲も卒なく業務は進めるものの、
組織の目的を議論したり、
「その目的にどう関わっていきたいか」を語り合う場は
一度もなかったのです。
その結果、こんな不安が常につきまといました。
・周りはどんな想いで働いているのかわからない
・自分だけやる気を出しても評価されないのではないか、頑張るだけ損なのではないか
・いざチームで挑戦しようとしても、温度差でうまくいかないのではないか
案の定、目的が共有されない職場では、
いじめや仲間外れ、ハラスメントが平気で行われたり、
それを見ても無関心な人が多くいました。
気づけば、私自身も「周りに無関心」になっていたのです。
何気ない日常会話や最低限の報連相だけでは、
共通の目的への意識や貢献意欲は伝わりません。
だからこそ、いざという時、一致団結しなければならない局面で、
組織は簡単にバラバラになってしまうのです。
必要なのは、もっと本質的な会話です。
「なぜこの仕事をするのか」
「私たちは何を目指しているのか」
「どうすれば互いの強みを発揮できるのか」
こうしたビジョンや貢献意欲を確認し合う会話があることで、
組織のベクトルはそろい、自然とモチベーションや信頼関係が高まります。
つまり職場におけるコミュニケーションは、
雑談で関係性をつくり、
業務会話で課題を解決し、
そしてビジョンや貢献意欲を共有する会話で組織を強くする。
この3層が揃ってこそ、
コミュニケーションは真に機能するのだと思います。
「今日はどんな会話をしているだろう?」
ぜひみなさんも職場で振り返ってみてください(^.^)
Fコードと社労士試験 〜プラチナチケットを手にした日〜
先日、前回のブログでお伝えしたとおり、
ついにアコギで“Fコード”を押さえられるようになりました(^.^)
この喜びをわかってくれる人は意外に少なく、
唯一、異業種交流会で初対面だったアコギ歴が私と同じくらいの男性だけが、
目をキラリと輝かせて共感してくれました笑
なぜ、こんなにも嬉しいのか。
……まあ、誰も私のFコード話に貴重な時間を割きたくはないと思いますが、
あえて今日はそのお話をさせてください(^^)
Fコードを押さえられるようになると、弾ける曲の幅が一気に広がるんです!
今まではFコードがある楽譜を避けていました。
ところが、弾けるようになると選べる楽曲の世界がぐっと広がる。
この感覚、実は社労士試験に合格したときの感覚ととてもよく似ているんです。
試験に合格するまでは「何者でもない」と感じていたのが、
合格した瞬間に「何者かになった」ような感覚になり、
そこから未来が一気に拓けていくように思えました。
もちろん、合格したからといって
開業してすぐ安定した売上を得られたわけではありません。
むしろ
「やっとスタート地点に立っただけ」
という厳しい現実もありました。
それでも、
「国家資格という自己実現のためのプラチナチケットを手に入れた」
というポジティブな捉え方をすると、
不思議とワクワクしかなかったのです。
私にとってFコードを押さえられたことは、
そのときの感覚と重なりました。
大げさに感じられるかもしれませんが、
私の心はそう感じてしまったのです。
人に否定されようが笑われようが、
自分の中では否定のしようがないんです。
……まあ、社労士資格が「本当にプラチナチケットだったのか」
は人それぞれでしょう。
でも、私にとっては間違いなく
今の仕事へと導いてくれた大切なプラチナチケットでした。
そして、Fコードは――
私をこっそりニヤつかせるささやかなプラチナチケットです(^^)
ギターを手に取り、部屋でポロン…とFコードを鳴らしながら、
「ふっ…俺はFコードを弾ける男なんだぜ」と、
ちょっとイキっている自分がいます♪
今は、そのFコードを武器にミスチルの「イノセントワールド」にチャレンジ中。
指がつりそうになりながらも、コードを押さえられるたびに
「俺、いけるかも…」とまたニヤついています。
そして迎える、サビ直前の
「ミス!ター!マイ!セルフ!」
興奮が最高潮に達し、つい力が入りすぎて
サビはストロークもコードもグダグダに…
その瞬間に――
ようやく自分がまだ「何者でもない」ことに気付かされます笑
大人が見落としがちな「小さな成功体験」
ついにやりましたよ!
アコギで“Fコード”を押さえられるようになったんです!
いやぁ…長かった。
最初に挑戦したときは
「こんなコード、指で押さえられるわけない!」
と絶望感しかありませんでした。
でも、ギター教室の先生が
「いや、できるよ。慣れが大事」
とそっと背中を押してくれた言葉が、
不思議と心に残って何度も練習を重ねました。
その結果、サッと押さえるにはまだ遠いものの、
指や手の形が“Fコードを覚え始めた”感覚があり、
ついにそれっぽい音を鳴らせたとき、
思わず叫びました。
「やればできるじゃん!」
自己肯定感って、
こんなふうに湧いてくるものなんですね。
これだけ聞くと
「子どもが補助輪なしで自転車に乗れたってくらいの話じゃないか」
と笑う人もいるかもしれません。
でも、大人になって仕事をするようになっても、
こんな言葉をよく耳にします。
「ブラインドタッチできないから、指二本で打つわ」
「傾聴は得意だけど、話すのは苦手」
「ITは苦手だから、若い人に任せよう」
「もう歳だから、覚えられない」
「忙しいから、新しいことを学んでいる時間がない」
文字にしてみると、
どこか“できない理由”探しをしているようにも見えます。
しかも、冷静に読むと、
大人の言葉なのにどこか子どもじみていて、
少し幼さを感じたりもします。
…正直なところ、かつての私自身もそうでした。
できない理由を並べることで、
自分を守っていたのだと思います。
でも、それでは一歩も前に進めなかった。
Fコードも、最初は「絶対無理」だったのに、
先生のひと言と、ほんの少しの継続が「できる」に変えてくれました。
社員教育も自己成長も、
実は同じことなんだと思います。
最初はできなくて当たり前。
誰かの後押しと、小さな成功体験の積み重ねで、
「できる」が「当たり前」に変わっていきます。
つまり――
「できるようになってからやる」
ではなく、
「やってみるからできるようになる」
大げさかに感じるかも知れませんが
Fコードがそれを身をもって教えてくれました。
小さな成功体験をつくる支援こそ、
社員教育で私たちが目指すべき姿なのかもしれません。
そして――
Fコードが押さえられるようになった私は
今夜もギターを片手に自己成長中。
…ただ、長女のアコギと次女のベースの腕前が見事なせいか、
私のFコードごときでは家族からは、心のこもっていない「へー」で軽く流されました笑
言葉の節々に現れる心の距離とは?
今回は、冒頭のいつものくだらない雑談と
本題がしっかり繋がっているという、非常に珍しい回です。
最初は本当にどうでもよい話しなのですが、
「くだらない!」
と言って途中で読むのを諦めずに、
なんとか我慢して読み進めてみてください(笑)
さて、「ワンチャン」という言葉をご存じでしょうか?
もともとは
「ワンチャンス(one chance)」の略語で、
「一度のチャンス」「可能性が少しはある」という意味。
「勉強してないけどワンチャン赤点はクリアできるんじゃね?」
「賞味期限2週間過ぎてるけどワンチャン食えるかも」
なんて使い方をするようです。
数年前、娘たちがよく口にしていたのですが、
私は「なんだその言葉は…」と違和感を覚えていました。
そこで彼女たちがその言葉を発するたびに、
「ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギさん」
とつぶやいて、よくからかっていました。
ところがあるとき、ふと思ったんです。
「犬はワンちゃん、猫はネコちゃん」
「なのに、なぜウサギは“さん”なんだ?」
「ウサギちゃん」とはあまり言いませんよね。
そこで他の動物をあてはめてみました。
「くまちゃん」「うしちゃん」「リスちゃん」
…どれも不自然。
やっぱり“ちゃん”が似合うのは犬と猫だけか、
と諦めかけたその瞬間、ついに閃いたんです!
「ハムちゃん!」
そうです、ハムスター。
実家で飼っていたとき、
親父が「ハムちゃん!ハムちゃん!」と
連呼してかわいがっていたのを思い出したんです。
つまり、“ちゃん付け”されるのは、犬・猫・ハムスター。(他にいたら教えて)
いずれも人間にとって癒しの存在であり、
家族のように近しい相手。
一方で、それ以外の動物は、心に少し距離を置いた存在。
更にその時に思い出したんです。
「これって、職場の人間関係にも似ている…」
実際、あるクライアントの部長さんが
こんな話をしてくださいました。
「Aさんが辞めるんです」
「なんか私に壁があるみたいで、私も壁を感じていたんです」
「『部長、お話しがあります』と言われたときに、あ、辞めるなと直感しました」
「案の定、退職の申出でした」
「いつか辞めるだろうなと感じていたのに、何もしなかった自分に腹が立つんです」
犬や猫、そしてハムスターのように、
自然と“ちゃん付け”できるほどの親しみやすさ。
それと同じように、
職場でも「安心して声をかけられる関係」が築けていれば、
辞める前に本音や悩みを打ち明けてもらえたかもしれません。
逆に「壁を感じる」状態では、言葉を交わしていても距離は縮まらず、
最後に「退職します」と告げられるだけになってしまいます。
その部長さんには
「今回のように2人でお話しがしにくかったら、私を交えて3人で雑談でもしましょう」
とお伝えしました。
やはり、人と人との距離感は大事――。
日常の小さなコミュニケーションの積み重ねが、
その差を生むのだと改めて感じます。
だからこそ必要なのが「承認」と「対話の習慣」です。
承認とは、大げさに褒めることではなく、
相手の存在や行動をきちんと認めること。
「見ているよ」「気づいているよ」
という小さなサインが、相手の心を開きます。
また、定期的な対話を通じて
「壁があるのでは?」と感じたときにこそ、
一歩踏み込んでみる勇気が大切だと感じます。
それが、離職を防ぐ予防策になったりします。
“ワンちゃん、ネコちゃん、ハムちゃん”のように、
自然と親しみを込められる関係性をつくるために、
承認と対話の力をもっと磨いていきたいですね。
…ただし現実の職場で「○○ちゃん」と呼ぶのは
セクハラと受け取られることもあるので要注意(^.^)
自己認識と他者認識のギャップがチームを強くする「持ち味発見ワークショップ」
先日、パソコンのマウスの動きが悪くなったので、
新しいマウスを購入しました。
それがこちらです。
↓↓↓↓
https://amzn.asia/d/2yp7oYa
エレコム マウス ワイヤレス (レシーバー付属) トラックボール 大玉 8ボタン チルト機能 ブラック M-HT1DRXBK
見た瞬間に「なんだこれ!?」と思わず声が出てしまうような異様な形。
まるでエイリアンの心臓のような、不気味ささえ漂います。
ところがこのマウス、実は普通のマウスとは全く違う動きをします。
本体を動かすのではなく、中央の「ボール」を指で転がしてカーソルを動かすのです。
なので、机の上が書類や資料でいっぱいで、マウスを動かすスペースがない…
そんなズボラな方にはまさにもってこいの一品です笑
しかも、フリーのボタンが複数ついていて、好きなショートカットを登録可能。
私は「コピー」「ペースト」「エンター」を割り当ててみましたが、
作業効率が一気にアップしました。
このマウスだけで仕事が完結してしまう感覚です。
ただ一つ、使ってみて困った点が…。
小さなボタンや細かい位置にカーソルを合わせるのが意外と難しいのです。
ボールを微調整しながら合わせるのですが、上手くいかなくて時々イライラすることもあります。
とはいえ、新しいツールは「慣れ」も大事。
しばらくはこの不思議なマウスを使いこなしてみようと思っています(^.^)
さてさて、
先日、クライアント企業様で「持ち味発見ワークショップ」を実施してきました。
これは自分の「持ち味=強み」を仲間から発見してもらい、
それを自分自身の成長につなげていく研修です。
面白いのは、必ずしも想定通りにならないこと。
「これが自分の強みだ!」と思っていたのに、周りからはそう見えていなかったり…
逆に「そんなところを評価されてたの?」と驚きがあったり…
そんなギャップから、新しい気づきや学びが生まれるのです。
みなさんもこんなこと、ありませんか?
・一生懸命やっているのに「そこは評価されていなかった」と知って落ち込む。
・何気なくやっていたことが「すごく助かってる!」と感謝されて驚く。
・自分の強みを活かしているつもりが、実は“独りよがり”になっていた。
実はこれ、誰にでも起こる自然な現象なんです。
なぜなら「自分が思う自分」と「周りが見る自分」は必ずしも一致しないから。
このワークが力を発揮するのは、こんな理由があります。
・自分では気づかない強みが見える(仲間の目線=ジョハリの窓)
・強みを活かす方が成果や幸福感につながりやすい(自己効力感)
・お互いを認め合う空気ができると、安心して発言や提案ができる(心理的安全性)
つまり、ただの“褒め合い”ではなく、根拠のある組織づくりの仕掛けなのです。
職場での取り入れ方としては
・具体的に伝える:「優しいね」ではなく最後まで話を聞いて要点を整理してくれるね」に言い換える
・小さな習慣にする:朝礼でGood&Newsの発表者に一言フィードバックをする
・次に活かす:発見した強みを「どの場面で使うか」を考えてみる
など仕組み化していくとより効果的になります。
「持ち味発見ワークショップ」は、“強みを見つける” → “取り込む” → “仕事で使う”
という流れを自然に作れる研修です。
みなさんの職場でも、こんな“気づきの循環”をつくってみませんか?
きっと、働く一人ひとりのやる気とチームの力が一段と高まりますよ(^.^)